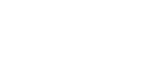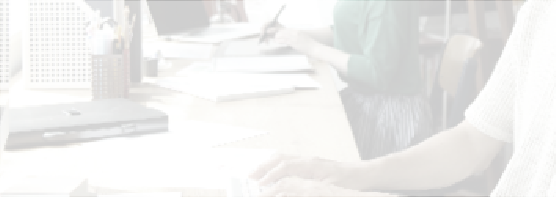不動産コンサル
05 12
2025
高騰する大規模修繕費
建設工事費の高騰により賃貸経営の大規模修繕費用負担が増加しています。
先日築35年の賃貸住宅の大規模修繕工事の見積もりを取ったら、
約1000万程度かかることが判明しました。
最初は本当かなと思いましたが?
この時代の建物には一般的ですが外壁全面にタイルが貼られており、
その補修費用を含むとこれくらいになってしまうようです。
これからますますコストが増える傾向にあり実行するか否か悩ましいところです。
不動産を複数所有する地主系のオーナーが必ずと言ってもいいほど保有しているのが、
この手の築年数30年を超える大規模修繕工事がかかる物件です。
長期間保有しているオーナーからすれば、物件にも愛着があり、
これから大規模修繕工事をして次の時代にも承継したいところですが、
四桁の費用負担をどう考えればいいのでしょうか?
この費用負担を賃料が上昇させる、あるいは維持するためのコスト
と思って判断するとなかなか難しい結論になってしまいます。
10世帯くらいの物件で世帯あたりの費用負担が100万円となると、
いくら賃料は維持されてもいつになったら回収されるのか?
という考え方になってしまいます。
これはキャッシュフローだけ、
つまりお金の出入りだけを考えればこのような考え方になるんですが、
もっと大事なことは大規模修繕工事を実施することが、
資産価値の維持につながるという視点です。
つまり大規模修繕工事は資産価値に反映され、
かかったコストは価値を維持するためのものであるという考え方です。
実はリノベーションや不動産再生を手掛ける会社はこの考え方で事業を組み立てています。
言うまでもありませんが、老朽化した不動産を取得し大規模修繕工事や、
リノベーション工事を実施し、それにさらに利益を上乗せして売却する。
常に資産価値に配慮しているからこのような判断ができるわけですが
不動産を売却や資産の組み換えをせず、
全ての不動産を保有前提で考えてしまうとなかなか理解できないかもしれません。
土地や建物多数保有する地主さんも、
今後全体の資産を維持しながら運営していくためにはこの視点が
どうしても欠かせなくなると思います。
全体の資産を棚卸しして、継続保有するものにはしっかりとした維持管理の手間をかける、
そして保有にこだわらず運用の視点で考える不動産は有効活用や、
売却による現金化、資産の組み換えを複合的に組み合わせて実践する。
建築費の高騰、そしてインフレによる資産価値の高騰は
そんな視点がとても大事だということを改めて教えてくれます。